| (現在の)浄土宗「法性寺」 | 小倉百人一首76番 | 最勝金剛院 |
 | 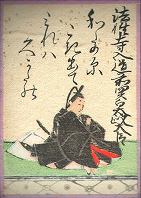 |  |
| 東山区本町16丁目(伏見街道沿い) 「説明板」が建っている | 法性寺入道前関白太政大臣(藤原忠通) | 後法性寺殿九条兼実の廟所「八角堂」 |
(東京から引っ越してきた人の作った京都小事典)
法性寺と法成寺
(INDEX:索引へ)
| (現在の)浄土宗「法性寺」 | 小倉百人一首76番 | 最勝金剛院 |
 | 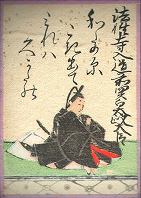 |  |
| 東山区本町16丁目(伏見街道沿い) 「説明板」が建っている | 法性寺入道前関白太政大臣(藤原忠通) | 後法性寺殿九条兼実の廟所「八角堂」 |
| 「法成寺址」の碑 | 「法成寺」の礎石 | 藤原道長と娘彰子 |
 |  |  |
| 府立「鴨沂高校」の塀沿いに碑を残すのみ | 左碑の近くにある清浄華院で「柱座」となる礎石が見つかっている | 「紫式部日記絵巻」から(背を見せる男性が道長、赤子を抱いているのが彰子) |