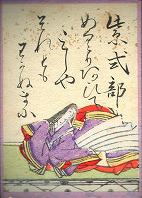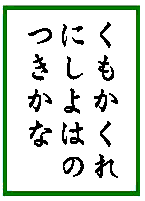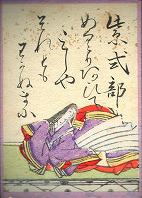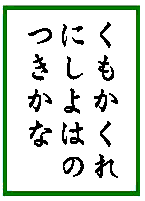57.紫式部
上の句順 下の句順 (INDEX)
| めくりあひて |
みしやそれとも |
わかぬまに |
くもかくれにし |
よはのつきかな |
| めぐり逢て |
見しやそれ共 |
分ぬまに |
雲がくれにし |
夜半の月かな |
| 巡り逢ひて |
見しやそれ共 |
分ぬ間に |
雲隠れにし |
夜半の月かな |
- ■歌について
- 昔の仲のよかった友が訪ねてきたのにすぐに帰ってしまった。そのときの残念な気持ちを詠った歌。
- ■出典
- 新古今集雑上
- ■作者略歴
- 生没年未詳。中納言藤原兼輔の曾孫、為時の娘。越後守藤原宣孝の妻。夫の死後一条院(986)中宮彰子(上東門院)に仕え、初めは藤式部。「源氏物語」を書いた頃から紫式部と呼ばれるようになった。筝をよく弾いた。
- 【補】
- 紫式部は曾祖父(堤中納言)藤原兼輔の邸宅(現在は「蘆山寺」、当時は「中川のわたり」と呼ばれていた)で生まれ育った。
- 上の歌は紫式部が越前に行く前だから、長徳2年(996)以前(23歳頃)に詠んだ歌。
- 紫式部の「友」と言えるのは、「大納言の君(源廉子か)」と「小少将の君(大納言の君の妹)」とくらい。この歌の友は「小少将の君」らしい。
- 紫式部は人生最後(に近い)頃、伊勢大輔とこのような和歌のやりとりをしている。
- 紫式部の墓は堀川通にあって、小野篁の墓と並んでいる(源氏物語は宮廷内部を書き過ぎたため「紫式部は地獄に」落とされた、それでは可哀想だから小野篁にお願いして「地獄から救い出して」もらった、という噂があって、近くに葬られたとか・・・)。
- 紫式部の歌はそれ程上手くないので(失礼)、歌が引用されることは少ない。源氏物語は有名であちこちに。宗達も屏風絵を描いている。
- 歌の名手藤原公任の前で歌を詠むときは“凄く緊張した”ようで、その様が「紫式部日記」に書かれている。その時の歌が『珍しき 光さし添ふ 盃は 持ちながらこそ 千代も巡らめ』だった。
角田文衛博士(私の尊敬する)推論による「作者略歴」
- 天禄4年(973)出生説が有力。とすれば清少納言より「7歳年下」ということになる。名前は「香子(たかこ)」の可能性が高い。
- 若き頃、伯父・為頼が摂津守に任命された(正暦3年(992))ことで「須磨、明石」を見聞した。母方の祖父・藤原文範が大雲寺の創建に関与したことで「北山」によく出向いた(この辺が「源氏物語」の素材になってくる)。
- 父・為時が越前守として赴任した折(長徳2年(996))、1年余り同行した(現在の武生)。
- 長保元年(999)藤原宣孝と結婚(第二夫人)。賢子を生んだ。宣孝は長保3年(1001)4月亡くなる。
- 長保4年(1002)になって「中川のあたり」で源氏物語を書き始めた(まず「帚木三帖」から書き始めたとも言われている。現存する物語の第1帖は「桐壺」ですが)。
- 源氏物語を書いていることを知った藤原道長(同じ藤原北家、康保3年(966)−万寿4年(1027))が紫式部を(18歳になった)中宮彰子の女房になるよう勧めた(寛弘2年(1005))。
- 寛弘2年(1005)12月29日から出仕した。
- 寛弘5年(1008)頃、藤原道長は紫式部と関係を持った。「紫式部日記」は寛弘7年(1010)夏〜秋にまとめて書いたもので、その中に自ら書いている。。
- (紫式部日記から−寛弘5年(1008)秋)朝、部屋から外を眺めていたところ、藤原道長が女郎花を手に現れたので
- 「女郎花 盛りの色を 見るからに 露のわきける 身こそ知らるれ(露が降りて美しく染まった女郎花の盛りの色を見ると、露が降りずに美しく染っていない私の身のことが恥じられます)」と詠むと
- 「白露は 分きてもおかじ 女郎花 心からにや 色の染むらむ(白露が「あなたと女郎花」を分け隔てて降りるわけではないでしょう。美しい色に染まるのは「あなたや女郎花」の心次第ではないですか)」と返されました。
- 「二人きり」でこんな微妙な「歌のやりとり」ができるのは、既に「一線を越えた仲」だったからでしょう(寛弘5年(1008)6月には「道長が紫式部の部屋まで訪れた」ことが書かれている)。
- 寛弘5年(1008)10月には「源氏物語」は脱稿したようです(約6年)。
- 彰子退位・門院宣下(万寿3年(1026))後も上東門院(永延2年(988)−承保元年(1074))に仕えた。紫式部の没年は長元4年(1031)頃と推定される。辞世の和歌は難しいが、長元3年(1030)頃の和歌か。
- (参考)山本淳子著「私が源氏物語を書いたわけ−紫式部ひとり語り」(平成23年(2011))も作者の経歴を「きちんと時間軸」に沿って書いてあります。